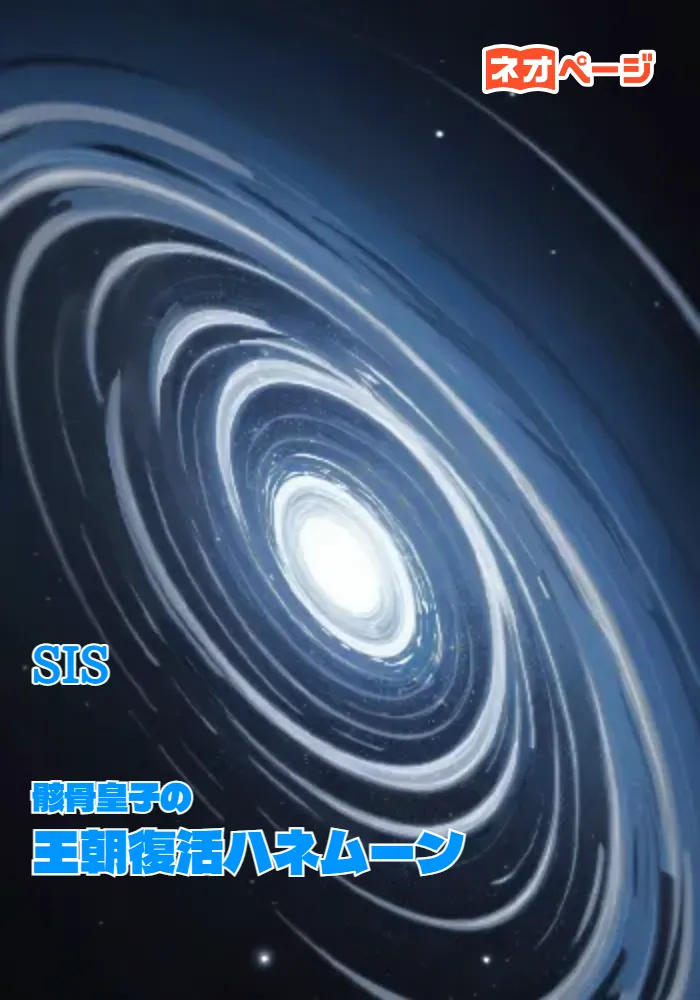 骸骨皇子の王朝復活ハネムーンSF·宇宙2024年09月21日公開日35,201文字連載中古代の浪漫を求める考古学者、ミスズ・クロカワは未知のステーションの調査中、裏切ったスタッフ達に襲われる。
骸骨皇子の王朝復活ハネムーンSF·宇宙2024年09月21日公開日35,201文字連載中古代の浪漫を求める考古学者、ミスズ・クロカワは未知のステーションの調査中、裏切ったスタッフ達に襲われる。そんな彼女を助けたのは、一万年の時を越えて現代に蘇った、機械の体を持った超古代の王子様。
アストラジウスと名乗る彼とミスズは契約を交わし、彼の王朝復活の為に協力する事になるのだが……。
『じゃあ、先に婚約しておくとするか?』
「ふえ?」
超文明の力で出来る事なら何でもできる皇子様と、未知を追い求める女性考古学者の宇宙を股にかけるハネムーンが始まる。
<毎日更新実施中です。ストックが尽きるまで>
<SF考証多めの作品です。専門用語は一部あとがきで補足説明しますが、わからない事があればご意見ください。>
ただその立場に生まれたというだけで、男は全てを望む事が出来た。
全てだ。ただし、本当の願いだけは決して叶わない。
それがどれだけささやかで慎ましい願いであっても、叶う事は無かった。
そう。男はただ、生きていたかった。
「皇子。では、もう一度確認しますね」
辺境に設けられた、秘密の宇宙ステーション。その中枢。
生命維持装置に繋がれた患者を前に、年経た白髪の技術者が端末を片手に語り掛けている。
患者はガラスの繭のような生命維持装置の中で、無数のケーブルに繋がれ、およそ人の形を留めてはいなかった。目も虚ろで、自発的な生命活動はおよそ不可能。心臓も、肺も、機械に繋がれなければピクリとも動かない。脳にすら異常があり、およそ正常な部位は存在しないといっても過言ではない。
彼は生まれた時から死んでいたも同然だった。だが、真に死んでいた訳ではないために、今日まで生かされてきた。彼の生まれた立場がそれを可能とし、同時に死に至る事を許さなかった。
しかし、それも限界が来る。
どれだけの手を尽くしても、生きていない者を生かし続けるのは限界がある。
技術がどれだけ進歩しても、人は生まれというものを克服する事はできなかったのだ。それは同時に宇宙を支配するほどの技術力を手に入れても、人体の完全解明と、何より人の意識の革新はならなかったという事である。
そして、そんな男の傍ら。生命時装置の棺の横に、奇妙な物が置いてあった。
鋼鉄の箱。その中には、金属で出来た骨格標本のようなモノが、眠るような姿勢で安置されている。何かの機械であるらしいそれには無数のケーブルが繋がれ、奇妙な事にその大半は別の機材を通し、半生者の男に繋がれていた。
「これより、貴方の生命活動の停止と同時に生体情報を、隣の金属義体に転写します。これは貴方の脳のみならず、全身を……それこそ遺伝子情報も含む全てを、可逆的な形で変換、圧縮するものです。そのすべてが人工的な無機物に置き換わるというだけで、皇子の肉体情報は変わりません。よって、理論上は貴方の人格は損なわれないはずです」
脳さえ在れば人格を保存できる、というのはもはや迷信の類だ。
病に侵された金持ちが脳をクローンに移植した結果、それまでの鋭敏な経営手腕を失い落ちぶれた。優れた人格者が主要な臓器に悪性腫瘍が見つかりクローニング臓器を移植した結果、人格が変化し暴力的に振舞うようになった。そういう例は後を絶たない。
技術の発展は人の秘密へと深く切り込み、それ故のどうしようもなさに行き詰まりを迎えた。人格とは脳だけでなく脊髄、内臓の活動、共生する細菌……そういった、人体全てによって構成されるものである。
それはすなわち、永遠の否定である。かつて想像されていたように、人の意識をデータ化し、死を越えた永遠の存在になる……そんな空想は、科学の発展によって否定された。
しかし人の憧れに際限はない。
肉体の全てが人を成すならば、それを余さず朽ちぬ形で保存すればいい。
そうやって開発されたのが、この義体だった。
しかし銀河すべてを手中に収めた一族の力をもってしても、生まれとは別にどうしようもないものがある。
時間だ。
この義体技術は生まれて間もなく、男こそがその第一例となる、その予定である。本来ならば男の立場で使われるべき技術ではない。
勿論、銀河を支配する一族の権力を持って、秘密裡に……それこそ皇子本人も知らぬところで人体実験は繰り返されてきた。数十、数百という犠牲者を積み上げて、それでようやく、実行可能というところまで漕ぎつけた。しかし、そこが限界でもあったのだ。
「……正直、私としてはお勧めはしません。この技術は、まだ理論実証段階です。本当に、無機物に転写した情報が元の人格を損なわず維持できるのか、実証時間があまりにも足りません。最悪、皇子を自認する別の何かが新たに生まれい出る可能性の方が高い。皇子の尊厳を踏みにじる結果に終わるかもしれません。それでも……よいのですか?」
語り掛ける医者の真摯な言葉に返事は無い。皇子と呼ばれる男は、自分の意思では指一つすら動かせないからだ。
だが、何かしらの形で意思疎通はできているのだろう。医者の物憂げな黒い瞳が端末を確認し、変わらぬ意思を見て取った彼は小さく肩をすくめた。
「……分かりました。皇子のご命令に従います。ええ。私も覚悟を決めました。……推定では、およそ3分ほどで皇子の生命維持は限界を迎えます。そうなったらもう後戻りはできません。……私も、できうる限りの手を尽くします。御覚醒後も、我々医師団と技術師全員で皇子を御支えします。ええ。そうです。例え生身でなくとも、金属義体に生まれ変われば皇子は自由に歩く事も、走る事も、剣を振るう事だってできます。貴方様の臨む事は全て、今度こそ本当に全てが叶う事でしょう。どんな夢だって、叶いますとも」
生命時装置が、低く唸りを上げ始めた。
医者の見立ては正しく、技術の粋を尽くた延命処置の果てが迫り、男の命が限界を迎えつつある。それを見守る医師たちは、静かにその様子を見守っている。今更、彼らに出来る事は何一つとしてないのだ。
生命維持装置の中で、男が静かに目を閉じた。
「おやすみなさい、皇子。そして、どうか今度こそ願いを思うがままに叶えるのです。貴方が望むように望む事を、全て成し遂げられますよう……」