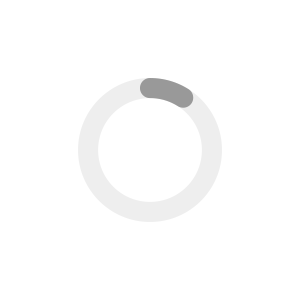
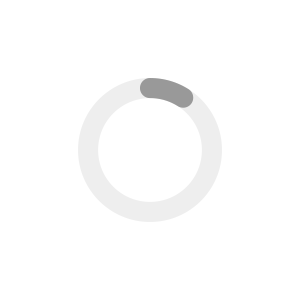
私とフィッシュの戦闘面での相性は正直あまり良くはない。
私はどちらかと言えば、一撃一撃に特化した一般的な近接アタッカー。
それとは違い、フィッシュは強化した身体能力にモノを言わせた連撃系の近接アタッカーだ。
私が一撃を当てようとする間に、向こうは3回ほど攻撃を当ててくる程度には攻撃回数に差が出ているし、その分私のHPも消耗するため、このまま正面からまともに戦えばただ負けるだけだろう。
恐らくだが、他のプレイヤーも似たように戦ってやられていったのではないだろうか。
だが流石に私も他と同じようにやられる気はさらさらない。
「あはッ!」
赤いオーラを纏いながらこちらへと突っ込み、両手にもったナイフで斬りつけようとしてくるのを紙一重で避け。
その顔の目の前で私は指を鳴らす。
瞬間、彼女の頭に非実体の羽が出現し視界を妨害するものの……彼女はそれすら関係ないというかのように、笑いながらそのまま攻撃を続行した。
元より視覚妨害が効かないかもしれない、というのは考えていた。
彼女は狼の獣人族。同じイヌ科の獣人ではあるが、私が気配察知の方向で元の狐という動物の特徴が表れているのに対し、彼女は恐らく嗅覚に現れているのだろう。
以前『惑い霧の森』で共に行動していた時にも、彼女が霧を見通せる私よりも早くモブを発見した事が何度かあった。
その時に決まって口にしていたのは『臭い』。これで違うなんて言われたら、それこそ身体強化系の魔術……部位を限定して嗅覚の強化なんていう限定的な強化魔術を創っていると言われた方がまだマシだろう。
型のようなものはなく我武者羅に振られているように見えるナイフを、私はしっかりと見て1つ1つ躱していく。
上から振り下ろされたナイフを身体を半分ほど捻るようにして避け、払うように振るわれたナイフを一歩後ろに下がることで避ける。
勢いを乗せて急所を狙い放たれた突きを【魔力付与】によって防ぎ、腹部狙いの蹴りを【血狐】に守らせる事でダメージを最小限に防いだ。
「おいおい攻撃してこないのかい?」
「そんな挑発されても、私の戦い方は変わりませんよ」
「あは、割と前衛タイプの子はこんな感じで言うと攻撃してくれるんだけどねぇ。アリアドネちゃんは純粋な前衛ってわけじゃないから仕方ない、かッ!」
「あっぶな!?……というか、あの時いた人狼化?みたいな魔術を使ってもないのにこっちを煽ってこないでくださいよ」
「痛いところを突かれちゃったなぁ。でもアレ一応私の切り札みたいなものなんだよ?……まぁ使うんだけどさァ!」
彼女の姿が変化し始める。
人の面影を残しながらも、獣の色を濃くしていく変化。以前も見たが、恐らくはその変化の代償にフィッシュは変化中動く事が出来ないのだろう、ご丁寧に自分から少し距離をとった後に変化を初めてくれた。
こうして出来た間に取った行動は、またしても攻撃ではなく準備だった。
「【ラクエウス】、【ラクエウス】、【ラクエウス】【ラクエウス】【ラクエウス】……!」
【ラクエウス】の多重発動。
これだけでもMPは結構持っていかれるものの、必要経費として割り切ることにして、急ぎながらフィッシュの周りの地面に落とし穴を設置していく。
何故攻撃しないのか?
一応理由はあるにはあるが……主な理由としてはこの場から離れるための下準備を優先したかっただけだ。
今もなお、目の前のフィッシュからは鐘の音が鳴り続けている。
正直耳が役に立たなくなってくるレベルで鳴っているのに対し、本人はどう思っているのか気になる所ではあるのだが……まぁそれは良いとして。
索敵をさせている【霧狐】が既にこちらに向かってきているプレイヤーを複数捉えているのだ。
元々は姿を隠し諸々の魔術を使えるように霧を発生させていたのに、音によって敵を集められたら視界を制限している意味がない。
向かってきているプレイヤーも倒せばいいのでは?という考えも一瞬過ったものの、それは却下、というより私のスペック的に無理だ。
どうしても私は1対1に特化している魔術ばかりを持っているため、複数との戦闘には向いていない。
それに加え、目の前の戦闘狂を相手にしながら他のプレイヤーも相手にするなど正気ではないだろう。
だからここはフィッシュの足止めが出来るものを用意し、この場から離脱。
その後、チクチクと向こうから見えない位置で【ラクエウス】による攻撃を行った方がまだマシだろう。
そう思いながら落とし穴をフィッシュの周囲に設置していると、彼女の変化が終わる。
どこか人の女性的なフォルムを残した人狼は、こちらを見て足に力を入れた。
そして地面を蹴り、飛ぶようにこちらへと向かってこようとした瞬間。
ずぼっ、という軽い音と共に、彼女は落とし穴を踏み抜いた。
落とし穴にも種類が存在する。
漫画で良く見る、所謂身体全てを穴に落とすものや、穴の中に竹槍などを仕込んで落ちたものを絶命させるものと様々だ。
その中でも、私が今回彼女の周囲に設置していたのは非常に浅い……深さにして足1つ分ほどしかない穴。
それを複数彼女の周囲に設置し、彼女は勢いよくそれに引っかかった。
するとどうなるか?答えは簡単だ。
びたーん、という擬音が似合いそうなほどに綺麗に彼女は地面に向かって勢いよくキスをした。
少なからずダメージも入ったようで、ふるふると震えている。
私はそれを見て少し居た堪れない気持ちになりながら、霧に紛れてその場から離脱した。
「あの、失礼します。……ぶふっ」
「アァアアアアアアアアア!!!!!!!」
一言、きちんと添えてから。